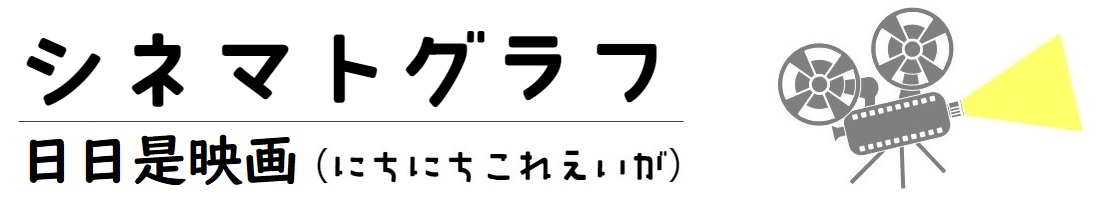| 原題 | Les amants du Pont-Neuf |
|---|---|
| 製作年 | 1991 |
| 製作国 | フランス |
| 監督 | レオス・カラックス |
| 脚本 | レオス・カラックス |
| 撮影 | ジャン=イヴ・エスコフィエ |
| 出演 | ドニ・ラヴァン、 ジュリエット・ビノシュ、 クラウス=ミヒャエル・グリューバー |
誰かが君を愛している
君が誰かを愛していたら
“空は白” と言ってくれ
相手は “雲は黒” と答えるだろう
それが愛の始まりだ
汚れた現実主義とロマン主義をどう組み合わせれば、こんな傑作が出来上がるのか?🤔
不浄なのに美的、大胆にして繊細、ミニマムだが壮大。まさにレオス・カラックスの才能が生み出した魔法🙂
綺麗でなくとも、美しくなくとも、彼の映像は誰にも真似できない芸術。
個人的映画史の中でも、ひと際輝く作品です📽️
そしてこのストーリーにも関らず、当時のフランス映画史上最高の製作費を掛けてしまった大事件は、凡人にはとても理解できません😓
(以下、続く)

この映画が出来上がるまでの本当の苦難を皆さんにも知ってもらうために、長文ですが簡潔にまとめました。
(以下、鈴木 布美子 著「レオス・カラックス 映画の二十一世紀に向けて」からの抜粋)
■レオス・カラックスへのインタビュー
【題名について】
『ポンヌフの恋人』というのは仮題だった。しかし製作途中で映画のことがマスコミで話題になり、仮題がそのまま正式な題名として定着してしまう。本当は “愛の埋葬” を暗示させる『Feu, l’Amour(=炎、愛)』という題にしたかった。(フランス語のFeuには “炎” や “撃て!” という意味の他に、死者の名前に付ける “故” という意味もある)
【ストーリーについて】
構想時には2つの感情があった。1つは朽ち果てて廃人となることや、死ぬことへの恐怖感。2つ目は思いがけないことに直面した時の感情。取り返しがつかない気持ちと、思いがけない気持ち。大事なのはイメージではなく、それらの感情をフィルムの中に再現すること。
僕が最も撮りたいものは躍動感と震えるような感覚。浮浪者のミュージカル映画を作ることは長年の夢だった。浮浪者は何も持たず、自分の身に何が起こるか分からない存在。パリに出てきたころは自分も浮浪者同然だったが、そういう存在に対する恐怖心もあった。誰かを愛し、何も必要としない状態のメタファーとして浮浪者を描いた。だからこれは僕たちの内なる浮浪者についての映画であり、貧困や本当の浮浪者を描いたものではない。
僕たちの一部であるこの世の悲惨さに目を向けることは、芸術家の義務なんだと思う。必要なのは、人間の貧しさを直視する視線であり、社会学的な分析者の視線ではない。
アレックスが眠りを奪われた存在なのは、自分が『汚れた血』を撮った後に睡眠薬なしに寝られない経験をしたから。ミシェルとアレックスが睡眠薬でカフェの客を眠らせるシーンでは、本当の睡眠薬を使った。ただ、その時使っていたハルシオンは今では禁止されている。
【エンディングについて】
自分の中のエンディングは、川に落ちた2人が泳いでヴェール・ギャランに辿り着き、雪を被ったしだれ柳の下で、もう一度話す。そしてアレックスはミシェルと別れなければならないことを受け入れる。そうすることで愛について何かを学び、心を開き、アレックスはミシェルとの別れを受け入れることで人間的に成長する。
制作の途中で恋人同士だったレオス・カラックスとジュリエット・ビノシュの仲が悪くなった時、「ミシェルは死ななくてはならない。そしてアレックスは30年後にポンヌフに戻ってきて、果たして自分は一度でも彼女を愛したのだろうかと自問する。」とカラックスが言い出し、しかし最終的にジュリエット・ビノシュの強い希望と、クリスチャン・フェシュネールが製作を引き継ぐ条件としてエンディングの変更を申し出たため、ハッピーエンドに変更せざるを得なかった。
■撮影監督ジャン=イヴ・エスコフィエへのインタビュー
前作と比べ、レオスがこの映画にポジティヴな要素を加えようとしたのは、しばしば彼の精神が喜びとは反対の状態にあったからだ。人は人生の中で、同時に幾つもの年齢を生きることがある。二十五歳の時に、十三歳であったり、六十歳であったりするのだ。レオスは若くして老成したというか、少し前までは、とても歳を取った人間のようだった。そして、彼は少しばかり本来の年齢に戻ったのだと思う。この映画で彼は、喜びにふさわしい年齢を見つけたのだ。
レオスの映画の主要なテーマは愛への恐れであり、愛することの困難さだ。愛が作り出す恐怖はあまりに大きいので、それを手なずけることはできないんだ。その恐怖が現れた瞬間から、物語はその恐怖を消そうと速度を増す。だから物語が愛を語るとき、そこには大きな恐怖があるんだ。最初にシナリオを読んだとき、そのエンディングには大いなる狂気があったが、とても美しいものだと感じた。だが、シナリオそのものが時間の経過によって擦り減り、エンディングの狂気は失われてしまった。だから本当はラストシーンを一番最初に撮っておけばよかった。
■制作時の大トラブル
初めは8mmフィルムを使い、『ボーイ・ミーツ・ガール』と『汚れた血』の中間くらいの予算感で映画を撮ることを考えていたが、それだと収益が期待できないためプロデューサー無しで製作しなければならなかった。だが『汚れた血』で協力したダアンとディアズがプロデューサーとなり、通常の32㎜フィルムで製作することになった。ところが、この映画がポンヌフ橋という現実世界を舞台にしていたため、小さな問題が積み重なった結果、映画そのものを予想を超えた困難へと導くことになる。
【膨れ上がる製作費】
フランス政府文化省にはCNC(国立映画センター)という機関があり、映画産業の管理と保護育成に当たっている。映画館のチケット料金の13%が特別税として徴収され、CNCに回される。そしてCNCはこの税金を財源として、製作、配給、興業の各分野に様々な財政的援助を行う。なかでも、芸術性の高い作品を対象とした援助システム(「avance sur recettes」と呼ばれる前貸し制度)は、提出されたシナリオを専門の委員会で検討し、一定の基準を満たした作品に対しては製作費を貸し付ける。制作側は、完成した映画が黒字になった場合のみ、借入金を返済すればいい。
この他にCNCは、徴収した税金の一部をIFCIC(映画・文化産業融資財団)の保証金プールに提供している。この機関は映画をはじめとする文化産業への融資の保証を専門に行う官民混合企業であり、株式は政府と大手金融機関が所有している。フランスには大手金融機関に属する映画制作専門の融資機関(ノンバンク)があり、IFCICによる保証を受けながら製作者への融資を行う。保証額は最大70%までで、これによって融資機関はリスクの大きい映画製作にも安心して融資できる。実際、融資した分が回収できずに、IFCICが負担する金額は毎年1200~1500万フラン(当時のレートで約10億円)に達する。そしてCNCはこの損失分に見合う金額を絶えずIFCICに補填しているのである。
1986年から行われているこの製作システムは、興業的ヒットが難しい「作家の映画」の保護に対して、極めて有効な手段となった。ヨーロッパ各国の中でフランスが唯一例外的に年間100本以上の映画を製作する地位を保っていられるのは、この官民一体となったプール・システムのお蔭なのである。
一般的にプロデューサーの手元に金が入るのは、製作した映画が完成し、配給会社やテレビ局などに権利が売れた時である。配給会社は購入金額を決めるが、完成したフィルムが渡されるまで支払は行わない。一方プロデューサーは、製作を開始した途端に現金が必要な立場に追い込まれるため、金融機関からの融資が必要になる。
『ポンヌフの恋人』の融資を主に担当したのはUFCA(映画・視聴覚融資連合)だった。UFCAはIFCICの保証以外に、製作費回収の目途がきちんと立っているかどうか、明確な基準を設けていた。ただしUFCAは金融機関であって映画の専門家ではないため、見積金額と回収の妥当性を保証するために大手製作会社のゴーモン社を共同製作者にする必要があった。
【UFCAの融資責任者パトリック・ゴンディネの弁】
IFCICの保証やゴーモンの承諾が無ければ我々はもっと慎重に検討したはずが、その2社の保護があったから出資することにした。後に製作がトラブルに陥った際も、とにかく映画が完成しなければ資金を回収できず大損するため、融資額が増えても完成することを望んだ。
【ゴーモンの配給担当者だったピエール=アンジュ・ルポガムの弁】
『ポンヌフの恋人』について最初に話をしたのは1987年の暮れでした。最初の交渉で、プロデューサーのディアズから提示された製作費の見積は2500万フラン(約20億円)で、そのうち800万フラン(約6.4億円)をゴーモンに負担して欲しい、残りは別の出資者が確定していると言われた。けれども最終的な契約の段階で、見積額は3200万フラン(約25.6億円)に膨らみ、それに応じてゴーモンの支払い額も1230万フラン(約10億円)に増やされた。
契約が交わされたのは1988年の6月で、1989年6月30日までにスタンダードのプリントをディアズから納品してもらうことになっていた。100万フラン(約8000万円)のみ先払いで、あとは納品後に支払う契約だった。
アンテヌ2、テレセーヌといったゴーモン以外の共同製作者も、ゴーモンと同様の支払い方法でリスクを回避しようとしていた。当時すでに、カラックスは危険な映画監督だという評判が立ち始めていた。『汚れた血』の撮影は期日も予算も大幅に超過しており、その原因を「カラックスの過度の完璧主義」とする空気が強かったのである。そうしたカラックスに映画を撮らせるなら、資金力がありカラックスをコントロールできるプロデューサーが担当すべきだと思われていたが、残念ながら出資者から見てダアンとディアズはそうではなかった。
映画業界全体が『ポンヌフの恋人』を不安視していた中で、結果的にCNCとIFCICの保証が企画実現の大きな推進力になっていた。また、文化大臣のジャック・ラングもカラックスの才能を高く評価していた。だが行政機関の介入は製作開始時だけでなく、やがて映画がゴールの見えない漂流を始めた時、CNCは実質的な調停者として何度も登場することになる。
■ポンヌフ橋での撮影
【プロデューサー ダアンの弁】
カラックスは最初、撮影のためにポンヌフを使う許可が簡単に取れると無邪気に信じていた。彼は全編を本物の橋の上で撮るつもりだった。私はとてもじゃないがそれは不可能だと思い、昼間の場面のみ本物の橋で撮り、全編の三分の二を占める夜間シーンはセットで撮影することにした。
夜間用セットの建造費を800万フラン(約6.4億円)で見積もった。
【美術監督ミシェル・ヴァンデスティアンの弁】
ある日、カラックスから電話がかかってきて「橋を一つ作ってくれ」と頼まれた。それで軽い気持ちで引き受けたのが、この大仕事の出発点だった。夜間用セットだと細部や遠景のスケールに神経質になる必要はなかったため、本物と同じ必要はなかった。ただ、適切な建設地が見つからず、最終的に南フランスのモンプリエ近郊のランサルグ村でセットを作ることに決めた。結果として、最悪の選択をしてしまった。初めてランサルグ村を訪れて350mというセットの規模を実感した時、恐怖心を覚え、だんだん怖くなってしまった。
用地使用の契約は問題なく運び、1ヶ月15,000フラン(約120万円)で借りることとなった。1988年6月に着工して9月に完成し、パリでのロケを終えたスタッフがただちにセットでの撮影を開始する計画になっていた。
一方で本物のポンヌフ橋は交通量の多い歴史的建造物であり、運輸省/内務省/文化省/パリ市/パリ警視庁など17もの政府機関の管轄になっていて、映画撮影を行うには著しい数の許可申請が必要だった。
交渉は1988年2月に開始したが許可が下りたのは7月で、撮影日は7月28日~8月15日の17日間となった。
■ドニ・ラヴァンの怪我
これが後の大トラブルの引き金となる事故である。
アクロバット練習のために靴のソールを削ろうとして誤って親指の腱を切り、とうやっても撮影開始に間に合わなくなる。この状況ついて保険会社と協議を重ね、以下4つの案が出された。
1. 製作をすべて中止して保険を支払う
2. ドニ・ラヴァンに代わる別の俳優を探す
3. 延期する(次に許可が下りる確証はない)
4. 別の場所で撮影する
プロデューサーのダアンは「4しかない」と思ったが、リスクが大きく自分から主張できないため、保険会社に提案させることにした。一方、保険会社は4の妥当性についてダアンに打診したところ「大丈夫」と回答したと言っており、意見は食い違っている。だが結果的に案4となり、夜間用セットを昼間用セットに作り替えるための差額900万フラン(約7.2億円)が保険会社から支払われた。
■ポンヌフ橋のセットの作り替え
ところが、昼間用セットへの変更には大きな困難が待ち構えていた。
昼間は陰影の影響で距離感が重要になるため、遠くの建造物まで作る必要があり、当初計画の2倍の面積が必要となった。
また、既に40台のブルドーザーを投入し、25万平方メートルの土砂を取り除き、地下水をくみ上げて人口のセーヌ川を作り、橋の基礎まで建造していたにもかかわらず、パリの太陽の方角に合わせるためにセットの中心線を変更する必要があった。
昼間用セットへの変更工事が始まって以降も、軟弱な地盤によって工事は難航した。また保険会社も複数あり、手続きが煩雑で支払いが間に合わない状況だった。このため、つなぎ融資を得るためにUFCAに頼るしかなかったが、つなぎ融資にはIFCICの保証は付かなかった。それでも保険会社が同席したことで安心したのか、UFCAは次第に融資枠を拡大していった。
しかし、6ヶ月経ってもまだ基礎工事が終わっただけで、ポンヌフは影も形も無かった。
まもなく保険会社は、契約に基づく中止損害金の1500万フラン(約12億円)を支払って撤退すると申し出た。
プロデューサーのダアンとディアズに打つ手はなく、映画を完成させるための資金の道は閉ざされた。


■資金ショート
ポンヌフ橋を使わないシーンをパリで先行撮影していたが、1988年12月に中断した。プロデューサーのダアンは中断理由を「撮影スケジュールのため」と弁解しているが、スタッフたちは皆「資金がどこかに消え、支払いが滞った」と言っている。当時ディアズが持っていた製作会社FPCの経営が悪化しており、資金を流用したという見方が強いが、詳細は分からない。ただ保険会社の担当者は、モンプリエの土木工事会社から「FPCを通さず直接支払うように」と要請されたことを認めている。FPCで資金が消えていることに気付いていたのかもしれない。
1989年になっても事態は改善されず、ランサルグ村の工事も3月には中断した。商業裁判所は管財人として弁護士のシャヴォ氏を任命し、撮影済みのフィルムの権利は彼の手に渡った。ダアンとディアズに残された手は、この映画を引き継ぐ新しいプロデューサーを見つける以外になく、完成までに追加で必要な資金を2000~3000万フラン(約16~24億円)と見積もった。
■新プロデューサー
撮影中断直後の1989年1月、ダアンはクリスチャン・フェシュネールに接触する。フェシュネールは映画のシナリオと撮影済みのフィルムを観て強く魅せられ、カラックスに今後の見通しを確認した。カラックスの説明は他の関係者の説明とは正反対だった。セットの完成は程遠く、撮影がまだ長くかかると述べ、バラ色の未来図を描くことはしなかったが、彼の分析は真実に思えた。フェシュネールは独自の検討をもとに、映画の完成までにまだ6000~7000万フラン(約50億円)必要だと算出した。そしてUFCAとIFCICと交渉し、この額の資金提供してくれるなら製作を引き継ぐ用意があると説明したが、まるで相手にされなかった。「ダアンとディアズの見積金額では映画は完成せず、あなた方は大きな損害を被ることになる」と説明したが、現実を直視できず安い見積の方に歩み寄ってしまった。ダアンとディアズは、一刻も早く製作を再開するために、追加資金をできるだけ低く見積もっていた。他の候補ではオデッサ・フィルムという製作会社を持つヤニック・ベルナールがいたが、彼の見積もダアンとディアズが提示した金額より高く、かつ提供できる資金はその額よりも少なかった。
一方、文化省やCNC、銀行などは、この映画を全面的に引き継いでほしいという話をゴーモンの社長ニコラ・セドゥ(レア・セドゥの大叔父)に何度もしたが、彼は「ノン」と言い続けた。
事態が急転したのは1989年6月。映画プロデューサーであるドミニク・ヴィニエのパートナーで、不動産業を営む資産家のフランシス・フォン・ビュレンが現れて2300万フラン(約20億円)を提示し、製作を引き継ぐことで合意した。これによってランサルグ村でもセットの建造作業が再スタートし、中断中に破損した箇所の修復が進められた。また、10月の撮影に備え、街路樹のプラタナスの葉を緑色に保存する薬品処理も必要だった。葉の付いた枝を切り落として薬品処理した後、再び幹に接着するという手法で、120本の街路樹にある9000本の枝を処理するだけで100万フラン(約8000万円)掛かった。
■2度目の中断
しかし、まだまだ問題は山積みで、財政がさらに悪化したFPC(ディアズの製作会社)を自己破産させ、この会社が抱える負債と映画を切り離す必要があった。その協議のために関係者を集めた会議が開かれたが、そこでビュレンの製作会社パリ・ア・ドゥが、当初の出資者たちから権利関係の合意を得ずに製作を再スタートしていることが分かり、出資者たちからの信用を失った。パリ・ア・ドゥにはきちんとした財政基盤が見当たらず、ビュレンが口先で「自分たちの資金で完成させ、公開後の利益を出資者に還元する」と言っても、その言葉を信用するわけにはいかなかった。出資者から見ると、パリ・ア・ドゥのやっていることは狂気の沙汰としか思えなかった。FPCの倒産によって『ポンヌフの恋人』の負債のみパリ・ア・ドゥが引き受ける義務が生じ、ランサルグ村の土木工事業者に対する未払い分も支払う必要がある。彼らに対してビュレンは手形で支払うと約束したが、結局支払いは行われなかった。ビュレンは撮影済みフィルムの権利が自身に無いことも理解しておらず、負債があることも知らず、かつ追加費用が大幅に不足していることも知らずに引き受けていたが、この時点で必要な追加費用は7000万フラン(約56億円)にまで増加していた。結局、ビュレンは製作を中止し、「カラックスとダアンを中心とした製作陣が新たな製作会社を設立するなら4000万フラン(約32億円)を提供する。ただし、その費用内で自分たちで完成させること。」という条件を出した。しかし、カラックス側の最終的な見積は8500万フラン(約68億円)というもので、この取引が実を結ぶことは無く、1989年9月に2度目の中断となった。
■漂流
映画が2度目の中断に陥った時、ランサルグ村のセットは完成に近づいており、残り2~3週間の作業が残っているだけだった。しかし1989年10月~1990年7月の10ヶ月間、セットにはヴァンデスティアンとその従弟しか残っていなかった。もし2人が出て行ったらセットは壊されており、映画はお終いだったはずだ。更に11月と2月の嵐によって、パニック映画のセットのように大きく損傷してしまった。
ジュリエット・ビノシュは1990年1月からエリア・カザンの新作の撮影に入る予定だった。初回のオファー時は『ポンヌフの恋人』が撮影中で断ったが、1年後に再オファーされた。それでも完成していなかったため断るしかなく、主演が決まらなかったせいか、最終的にカザンの企画自体が無くなってしまった。
資材会社・建築会社からランサルグ村の飲食店に至るまで、セット建造にかかわった地元企業や商店の多くに未払いのツケが残され、その総額は1000万フラン(約8億円)に達すると見られた。


■マスコミとの闘い
2度に渡る中断と増え続ける予算は、マスコミの格好のネタとなった。マスコミはこの問題の原因をカラックスの謎めいた完璧主義な人間性に結び付けようとしたが、すべての関係者はそれが原因ではないと否定した。これに対しカラックス側は、撮影済みの30分程度の未編集フィルムを使った試写会を開き、サミュエル・フラー、スティーヴン・スピルバーグ、ジャン・ルーシュ、パトリス・シェロー、フィリップ・ガレル、アンリ・アルカン、ジャック・モノリらを招いた。それを観たガレル、アルカン、モノリらは映画を絶賛するが、それがマスコミに取り上げられることはなかった。
■フェシュネールの登場
この問題に終止符を打ったのは1度目の中断時に候補に挙がったクリスチャン・フェシュネールである。当初は金融機関に一蹴された彼の見積は、結果的に唯一「現実性」を持っていることが証明された。フェシュネールは2度目の中断直後からカラックスと話をしていたが、「世論が高まって文化大臣がポンと大金を出してくれる」「日本から出資者が現れる」といった奇跡のような解決策を期待しているカラックスに対し、まずは現実を直視するよう信頼関係を作り上げることから始めた。また複雑怪奇な法的権利を解きほぐす作業を始めた。どこに幾らの負債があり、誰が何の権利を持っているのか、それらをすべて清算し、映画の権利を得るにはどれだけの費用が必要なのか、入念に調査した。
1990年5月。カンヌ映画祭の裏で、前プロデューサーのフォン・ビュレンとフェシュネールの交渉が大詰めを迎えた。フェシュネールの計画と要求は大きく以下の5点である。
1. 映画の権利買戻しに170万フラン(約1.4億円)
2. 製作を再開するまでに支払う負債の返済費用が530万フラン(約4.3億円)
3. 製作費を償却した後の利益の5%をパリ・ア・ドゥに支払う
4. パリ・ア・ドゥは受け取った権利金のうち150万フラン(約1.2億円)を負債の返済に充てる
5. パリ・ア・ドゥは映画のクレジットに社名を表記する権利を放棄する
この5項目のうち、ビュレンのパートナーであるヴィニエが最後の2項目に難色を示した。150万フランの負債の大部分はセットに資材を提供した地元企業のもので、その負債は製作開始前に精算することが明記されていた。それに対してヴィニエは分割払いで返済すると主張したため平行線をたどり、一旦は決裂してしまう。
しかしその晩、CNC長官であるドミニク・ヴァロンは「ジャック・ラング大臣はカンヌ映画祭の終幕までに両者が合意することを願っている」とヴィニエに伝え、翌日CNC長官のドミニク・ヴァロン、IFCIC代表のジョルジュ・プロスト、UFCAのパトリック・ゴンティネが協議し、フェシュネールが資材会社に関する負債を直接支払い、代わりに映画の権利を90万フラン(約7200万円)に下げて買い取る妥協案を提案した。この案をフェシュネール、ビュレン、ヴィニエが合意し、8ヶ月近く続いた中断は終わりを迎えることになる。
しかし、問題は完全に終わっておらず、CNCのお墨付きで再開案が合意されたにも関わらずUFCAはフェシュネールに対して一切の融資を拒否したのである。融資の道を閉ざされたフェシュネールは、これまでに製作した映画の権利をすべてジェネラル・デ・ゾー(ビデオソフト会社を傘下に持つ豊富な資金を持つ企業)に売却し、売上金の一部を製作費に回すことに決めた。これに対し一部の好意的メディアは「これは数字に対する勇気の勝利であり、経済に対する夢の勝利なのだ」と報じた。
■再開
ランサルグ村のセット建造は1990年6月に再開され、8月にはフランス映画史上最大のセットが無事完成した。ポンヌフ橋の巨大セットの脇には、地下鉄の通路のセットも作られた。クランクインから丸2年以上が過ぎた8月27日、ついにセットでの撮影が開始された。撮影は予定通り進められ、11月末にはクリスマス場面のために1週間かけてセットを人口の雪で覆いつくした。雪の素材は塩とメルトン(柔らかなフランネル生地)で、質感の違いを出すために、地面の雪には粗塩、欄干に積もった雪には精製塩、そして遠景の部分にはメルトンが使われた。
12月22日の夜、セットでの最後の撮影が終了し、残すは年明けにパリに戻ってラストシーンや刑務所の場面を含む幾つかの細かい撮影を残すだけだった。そして、南フランスの片田舎に出現した「人口のパリ」は、年明けすぐに解体された。


セットとは思えないポンヌフ橋からの夜景

Googleマップでは、史跡として今なおその痕跡が残っています。
Googleマップのリンク
■結末
撮影がまだ行われていた1991年2月。フェシュネールとカラックスの関係は悪化し、4月になると口をきくことはなかった。
恐らくカラックスから見れば、フェシュネールは資金力があり、計算高いプロデューサーでしかなかったのだろう。確かにフェシュネールは道義心だけで『ポンヌフの恋人』を救ったわけではなく、ビジネス上の計算も含めてこの映画を引き継いだ。彼は話題作りに役立つと思えば、関係者の証言を集めたドキュメンタリー・フィルム(そこにはここに書かれているような生々しい話は当然含まれない)を作るくらいはするだろう。一方、カラックスにとって理想のプロデューサーとは、ダアンのように興行的に困難な映画作りを積極的に後押ししてくれる理想家肌の人間であり、フェシュネールのような洗練された実業家ではなかった。
【フェシュネールの弁】
プロデューサーは監督から感謝されるために映画を作っている訳ではない。けれでも今回の場合、私は通常のプロデューサー以上の仕事をしたつもりだ。私が引き受ける前、映画関係者でカラックスを信用する者はいなかった。そのような状態にあった彼を救ってやったつもりだ。だからせめて彼には「ありがとう」の一言くらい言ってもらいたいものだ。
【ジュリエット・ビノシュの弁】
レオスはフェシュネールにお礼を言わないどころか、フェシュネールが払った努力に満足している様子すら見せなかった。そして、私の心もレオスとこの映画から離れてしまった。私は心の中でこう思った。「あなたの映画を作りなさい。あなたが望むものを。私は自分の役をやるわ。これからは、もうお終いよ。」とね。
ビノシュとフェシュネールがラストシーンの変更を要求した件は先に述べたが、フェシュネールはナンテールの浮浪者施設の場面もカットするよう要求していた。それは営業上の懸念に加え、浮浪者の行動に比べて俳優の演技が意図的に見えてしまうと思ったからだ。しかし、カラックスはラストシーンとは異なり、この要求は拒絶した。
■公開
1991年10月16日。『ポンヌフの恋人』はフランスで公開された。この映画はカラックスにとって非常に私的な映画であり、私的なヴィジョンを作品化することは、あらゆる代償を払ってでも達成されなければならない命題なのだ。そして、多くの人々が彼の信念に戸惑い、経済合理性に疑問を持ちながらも、最終的には彼の才能を受け入れた。恐らく最初の関係者の中で、この映画がこのような大作になると予期した者は、誰一人としていなかっただろう。まさに、『ポンヌフの恋人』は、映画という商業的システムの中で、ひとつの才能が徹底的に作家であろうとすることの栄光と矛盾を象徴する事件だったのである。
■最終的な製作費
初回契約時の予算3200万フラン(約25.6億円)に対し、最終的に1億6000万フラン(約128億円)掛かったと言われている。
これに対し、興行収入は公表されていないので分からないが、回収するのは到底不可能だったはず。この事件によってカラックスはフランスで10年近く資金調達が不可能となり、金融機関も「作家主導リスクの失敗例」としてこの映画を挙げ続け、フランス映画の資金調達モデルの広範な脆弱性を示す実例となった。
公開当時は映画自体も大きな批判に晒されたが、日本で27週ロングランを記録したように徐々にカルト的人気を博し、2000年代の再上映やソフト販売を通じて今でも部分的に収益を取り戻しているが、それでも赤字を解消することは困難でしょう。
2025年12月には4Kリマスター版が日本でも公開されました。