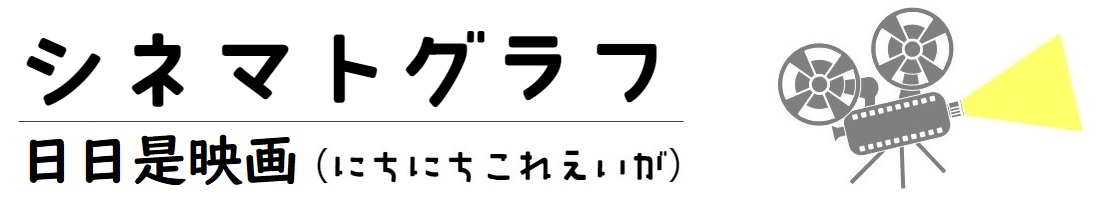| 原題 | Orlando |
|---|---|
| 製作年 | 1992 |
| 製作国 | イギリス・ロシア・イタリア・フランス・オランダ |
| 監督 | サリー・ポッター |
| 脚本 | サリー・ポッター |
| 音楽 | サリー・ポッター、 デヴィッド・モーション |
| 出演 | ティルダ・スウィントン、 クウェンティン・クリスプ、 シャルロット・ヴァランドレイ、 ヒースコート・ウィリアムズ、 ジョン・ウッド、 ロテール・ブリュトー、 ビリー・ゼイン |
この映画を20代の頃にレンタルで観て、大絶賛(数少ないAAA!)していた自分が誇らしい。
今観たら “不思議な映画” という印象が強いが、性別を超えて400年を生きた人間を、当時無名だった監督が壮大に描いてみせたというだけで評価に値する作品だと思う。本当に何の実績もない監督が、どうやってこの映画を作り上げたのでしょうか?
残念なのは予算の都合上93分という短さなので、語り切れていない点。もし実績ある監督が2010年以降に作っていれば、180分以上で編集しても余裕で許されたでしょう。
憂いと幸せの隔たりはナイフの刃一枚の厚さ
それでもこの映画は、普通の人間では体験しえない “複数の時代”、”複数の国”、”複数の文化”、”複数の身分”、そして “複数の性別” を一人で経験した「超越した人間」を描くことで、我々に非現実を見せる映画体験を提供してくれる。
そんな超人的な主人公でも異性の感情を理解できず、恋破れて人間的な弱さを見せ、遥か東方の国で研鑽に励む姿を映し出す。
そこでも最後には挫折を経験し、再び7日間の眠りにつく。
前と同じ人間。何も変わらない。性が変わっただけ。
現在なら性別や身分は変えられるとしても、通常我々は “一つの時代”、”一つの国/文化(アイデンティティ)” に縛られもの。普通の人は縛られることによって多くの不都合が生じるが、この映画の主人公は歳も取らないし基本的に自由だ。だから目覚めて女性になった時も、そのことをまるで意に介していない。けれど実際は生きる権利を奪われるほどの不都合が生じるという皮肉が、現在まで連綿と続いている社会問題を映し出す。
私は結局この世紀の精神に負けたのよ
原作を書いたヴァージニア・ウルフの時代であれば、女性である限り不都合は解消されない。それがこのセリフに集約されている。
でもこの映画がラストに見据えた21世紀では、未婚の女性でも子供を設け、生計を立て、自立することができる。それがサリー・ポッター監督が原作を超えて描きたかったことなのかもしれません。
原作はヴァージニア・ウルフだけあって、ストーリーを彩るのは溢れ出る言葉の数々。
それを中性的な魅力のティルダ・スウィントンが、時折我々を真っすぐ見据えて語り掛ける。
ちなみにエリザベス女王に扮したのはイギリスで有名なバイセクシャルの男性。
また、主人公の詩を酷評した詩人グリーンと、主人公の著作を評価した編集者を演じたのは同じ俳優だそうだ。