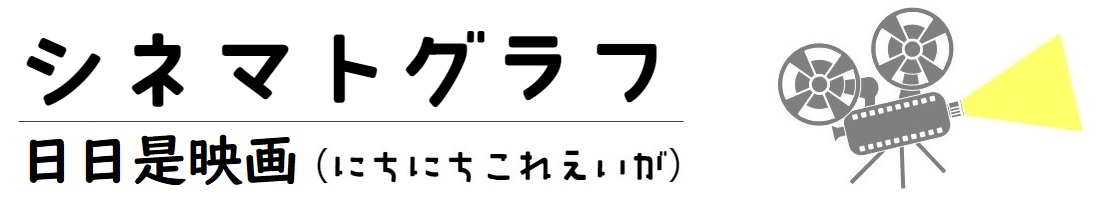| 原題 | Quand vient l’automne |
|---|---|
| 製作年 | 2024 |
| 製作国 | フランス |
| 監督 | フランソワ・オゾン |
| 脚本 | フランソワ・オゾン、 フィリップ・ピアッツォ |
| 音楽 | エフゲニー・ガルペリン、 サーシャ・ガルペリン |
| 出演 | エレーヌ・ヴァンサン、 ジョジアーヌ・バラスコ、 リュディヴィーヌ・サニエ、 ピエール・ロタン、 ガーラン・エルロス |
真実は私たちが見ているものではなく
私たちが見ようとしているもの
そして隠されているものかもしれない
映画は教会の説話で始まる。
「マグダラのマリアは罪深い娼婦だったが、イエスと出会い悔い改めた」という誤った解釈が一般化していた時期があり、それが映画の大きなテーマになっています。
ミシェルは孫のルカを溺愛しているが、娘のヴァレリーとはうまくいっていない。
電話の会話、家の出迎えだけで、既に不穏な空気が漂う。
そして、キノコに詳しくない老人が採ってきたキノコ料理には注意が必要ですが、案の定、娘を毒殺しかけて親子の亀裂は決定的になってしまう。
親友の息子ヴァンサンは刑務所帰りだが、何の罪だったか映画の中では伏せられている。
ミシェルはなぜかヴァンサンを気にかけ、親友に黙って金銭的支援までしている。
オゾン監督の作品は抑制された緊張感を漂わせ、最小限の会話で物語を進めていく。
物語の核心は最後まで見えないが、観客と登場人物の周りには既に核心を捕らえる網が静かに張り巡らされている。
真実を語らず、疑念を植え付け、罪を想像させ、言葉にされていない世界を膨らませる。
批判も教訓もなく、救済することもなく、詳しい説明もなく、どう理解するかは観る人の解釈に委ねられる。
ただ、彼らの選択、矛盾、過ちを静かに描く。
善と悪は綺麗に分けられず、曖昧になり、時に打ち消し合うこともある。
オゾン監督の作品はミニマルながら完璧な作りで、今回も我々を思索の旅に誘(いざな)ってくれます。
ところで、ミシェルが出会ったイエスとはヴァンサンだったのだろうか。
とても聖人とは思えないが、マリアが助けた時のイエスも “誰も見向きしない人” だったので、そういうことなのか。
また、主人公のミシェルと孫のルカは聖人の名ですが、娘のヴァレリーは違うので、そこにも意味がありそう。
本作とは関係ありませんが、昨日観た『ファントム・スレッド』とは、まさかの “毒キノコ繋がり” という偶然でした。