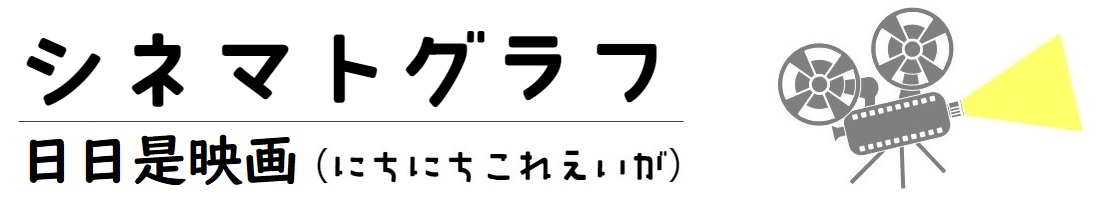| 原題 | Talk to Her |
|---|---|
| 製作年 | 2002 |
| 製作国 | スペイン |
| 監督 | ペドロ・アルモドバル |
| 脚本 | ペドロ・アルモドバル |
| 音楽 | アルベルト・イグレシアス |
| 出演 | ハビエル・カマラ、 ダリオ・グランディネッティ、 レオノール・ワトリング、 ロサリオ・フローリスジェラルディン・チャップリン、 パス・ベガ |
ペドロ・アルモドバル監督が意外にもオスカー(脚本賞)を手にした作品。
単独での受賞というより、以前の作品も含めてスペインで独自に花開いたアルモドバル・ワールドに対する長年の功績が評価されたのかもしれませんが、世界的に認知されるだけでなく、その尖った才能が幅広く認められたことは間違いありません。
前半から中盤までは、少し不穏ですが表面上は “無償の愛と友情の物語”。
しかし終盤に際ど過ぎる驚きの展開が待っており、やはりアルモドバル作品は一筋縄ではいかず、攻めた問題提起と表現に圧倒される。
この映画は一体何を描いていたのでしょうか?
遡ること12年。
同性愛者であることを公言しているアルモドバル監督は、『アタメ』という作品で異性愛を皮肉的に表現しました。
常に女性に焦点を当て、女性を大切に扱ってきたアルモドバル監督から見ると、女性に対する男性の行為は一方的で、暴力的で、短絡的で、束縛を愛と勘違いしているようです。
そして『トーク・トゥ・ハー』もアルモドバル作品には珍しく男性が主人公で、表面上は男性から女性への異性愛を描いていますが、『アタメ』とまったく一緒で男性は女性の真の愛を得られておらず、愛というより相手に対する崇拝・執着・魅惑、そして自己犠牲を厭わない自分を愛しているようです。
この映画の2人の男性マルコとベニグノは、タイプはまったく違いますが2人とも献身性に溢れ、そして “弱い” 人間です。
冒頭で2人はピナ・バウシュによる舞踊『カフェ・ミュラー』を鑑賞し、マルコだけ涙を流しますが、その意味は後で考察しましょう。
マルコはリディアを愛しながら、復縁したと主張する元彼エル・ニーニョが現れると、思い当たるリディアの言葉があったとはいえ、あっさりと身を引きます。
愛は深かったが執着心は深くなく、他者を気遣う優しさを見せたのかもしれません。
ベニグノはアリシアを愛しながら、家まで付けたり、ヘアクリップを盗んだり、将来2人が同居するために部屋を改装しようとします。
愛は一方的に深く、それ以上に執着心も深い。
それは優しさなのか? 変質的なのか? アルモドバル監督は愛と呼べなくはないギリギリの境界を描きます。
でも2人とも女性を愛していることに変わりはなく、結果的に目を覚ましたのはアリシアで亡くなったのがリディアだったように、何が良くて何が悪いか結局分からない。
この、”一方的な愛”、”正解のない愛” という点が、アルモドバル監督が描く異性愛なのです。
この映画ではここから更に別の2つのプロットが加わります。
1つはマルコとベニグノの奇妙な友情で、観る人によっては “同じ運命を背負う連帯感” を超えた同性愛を感じるかもしれません。
面会シーンではガラスに映る2人の顔を重ねて “何か深い意味があるのか?” と観客を惑わせますが、結果的にベニグノは同性愛者を装っているだけなので(両性愛者の可能性もありますが…)、2人の関係は友情なのでしょう。
ですがここもアルモドバル監督ははっきり描かずぼやかし、”同性愛的な友情の方が最後まで堅固だった” と示しています。
異性愛より同性愛の方が平和だと暗に言いたいのです。
そして最後のプロットは “妊娠” です。
誰が妊娠させたのか? は一切分からないし、推測することに意味もありません。
意識の無い女性を妊娠させるプロットを単なる事件として扱うのは映画的にどうかと思いますが、この事件によってベニグノは命を絶ち、アリシアは息を吹き返し、マルコはアリシアと近づいてしまう。
ここまで来ると、正しい愛が何かも分からないし、確かな運命も分からない。
アルモドバル監督は、その “不確かさ” を描きたかったのかもしれません。
最後に、なぜ冒頭でマルコは涙を流したのでしょうか。
アルモドバル監督の多くの映画では本物のアーティストの歌唱/演奏/踊りが差し込まれるように、舞踊を観て涙を流し、民族歌謡を聞いて感動するマルコの姿を通じて、芸術に対する感受性を描きたかったのだと思います。
一方でベニグノはアリシアに言われて映画を観るようになりますが、芸術に対する受け取り方は少しマニアックでした。
芸術を愛したマルコとアリシアは生き残り、最後に出会い、新しい人生を歩む。
そういう事なんだと思います。