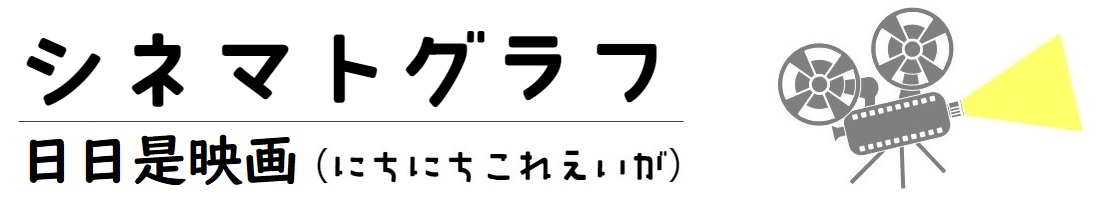| 原題 | The Monk and the Gun |
|---|---|
| 製作年 | 2023 |
| 製作国 | ブータン・フランス・アメリカ・台湾 |
| 監督 | パオ・チョニン・ドルジ |
| 脚本 | パオ・チョニン・ドルジ |
| 撮影 | ジグメ・テンジン |
| 出演 | タンディン・ワンチュク、 ケルサン・チョジェ、 デキ・ラモ、 ペマ・ザンモ・シェルパ、 ペマ・ザンモ・シェルパ、 タンディン・ソナム、 ハリー・アインホーン |
『ブータン 山の教室』の監督でもあるパオ・チョニン・ドルジは、優れたストーリーテラーだ。
この映画でも、「なぜ僧侶が銃を必要とするのか?」観客に最後まで分からせない。
そして、民主化という深いテーマを描きながら、ブータンという貴重な文化と風土を生かすことで、民主化の弊害・期待・不安を分かりやすく伝えている。
2006年、”幸せの国”、ブータン王国。
インターネットとテレビが無くとも国民の多くが幸福だった楽園に、いよいよ民主化が訪れようとしている。
世界の人々が命がけで望むものを与えられたのよ?
でも今でも幸せだし、私たちが命をかけなかったのは必要ないからでは?
なぜ、100年に渡り平穏を保ってきたブータン国王は自ら譲位し、総選挙を実施したのか?
恐らくは世界の歴史に学び、”権威主義より民主主義の方がマシ” と考えたからなのでしょう。
既に国内で政治腐敗が始まっていた可能性もあるし、権威主義大国である隣国に取り込まれてしまうと危惧し、その前に手を打ちたかったのかもしれない。
実際1900年前後に清国とロシア帝国の干渉を受けており、イギリスの支援で撤退させた歴史がある。
国の将来のために権力の一部を手放すという英断を下せるのは、優れた国王である証でしょう。
このような背景があった上で、ストーリーの中心は “民主化に向けた初めての選挙” だ。
ここで起きる出来事は非常に示唆に富んでいる。
簡単に言うと「民主化=選挙=分断」。
今、民主国家で起きている事象を、とても端的に言い表している。
極論を言うと、「分断を嫌がって権威主義となり自由を失う」か、「分断してもいいから自由を得る」かの選択なのだ。
選対委員のツェリンは極端だが、おそらく国王もドルジ監督も、”痛みは伴うが、未来はこの先にある” というツェリンと同じ考えなのだろう。
まさかあの僧は銃を撃たないよな?
どうだろう?奇妙な時代だから。
そこに “銃” という、もう一つの弊害の象徴が現れる。
権威主義だろうが民主主義だろうが、イデオロギーが生まれれば衝突が起き、暴力が生まれる。
「この銃は多くの国民を殺した」というセリフがあるように、1800年代の終わりに内戦も経験している。
そして、民主主義の象徴アメリカの銃社会を見れば、民主化を恐れる気持ちも良く分かる。
上のセリフは、銃収集家のアメリカ人の懸念に対して通訳が返した答え。
ブータンでさえ時代と共に道徳観念が変わり、不確実性が増しているのかもしれない。
憎しみ、争い、苦しみ
私たちが苦難を乗り越え、慈悲心と平和がその3つの毒に打ち勝ったことを示すためだ。
“選挙” と “銃” という2つのストーリーにうまく取り入れ、ユーモアを交えながら示唆に富んだ物語を作る。
しかも、ラストまで “銃” の目的が分からない。
「ラマ僧は最後にAK47を乱射するんじゃないか?」という不安さえ抱かせる。
とても秀逸な脚本でした。
ちなみに銃収集家のアメリカ人ロナルド・コールマンは、『失われた地平線』の主人公に使われた名前。
この小説から「理想郷=シャングリラ」という言葉が生まれ、1937年にはフランク・キャプラによって映画化されている。
つまり「理想郷=ブータン」に押し入ってきた白人という意味になる。
これだけ平和的に、美しい風景と共に、民主化と暴力について考えさせる映画は、ブータンでなければ作れなかったのかもしれません。