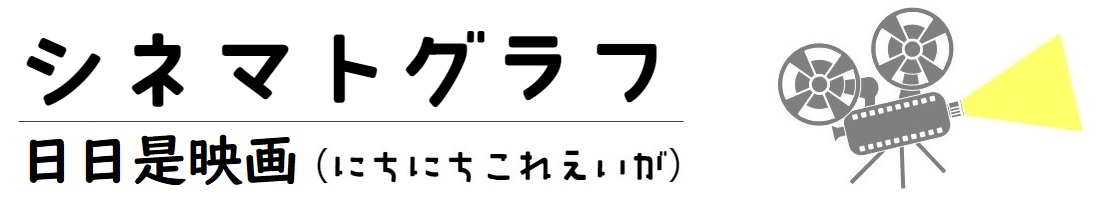| 原題 | The Wild Robot |
|---|---|
| 製作年 | 2024 |
| 製作国 | アメリカ |
| 監督 | クリス・サンダース |
| 脚本 | クリス・サンダース |
| 音楽 | クリス・バワーズ |
| 出演 | ルピタ・ニョンゴ、 ペドロ・パスカル、 キット・コナー、 ビル・ナイ、 ステファニー・スー、 マーク・ハミル、 キャサリン・オハラ、 マット・ベリーヴィング・レイムス |
2016年に発刊された児童向け小説「Wild Robot」が原作。
このアニメは他のアニメにありがちな子供向けのジョークはほとんどない。
コミカルな場面にもすべて意味が込められており、何らかの示唆が含まれている。
スカンクの真似をするシーンですら直後に技術的な会話があり、キラリが「それって大丈夫なの?」とロズの心配をする。
そして生き物の生死から目を逸らすことなく、死も含めてしっかりと描いている。
「大人も楽しめるアニメ」の域を超え、原作の意図をしっかり汲んだ「大人の知性にも耐えられるアニメ」です。
期待せずに観たら、ビックリしました。
テーマは “自然”、“成長/子育て”、“変容”、“アイデンティティ”、“論理と感情”、“受容”、“愛と犠牲”、“知性”、などでしょうか。
とにかく多様な内容が含まれています。
【自然】
冒頭から食物連鎖を何度も描き、自然の厳しさをそれとなく伝えます。
ロズはプログラム通りに動こうとしますが、キツネのチャッカリも「僕はキツネらしく卵を獲るのさ」と言い放つ。
それが野生動物のプログラムであり、自然界には何の悪意も存在しない。
【成長/子育て】
ロズは冒頭でカニの真似をして逃げるように、他の動物を真似て生き延びる。
人も動物も、初めは親の真似をして成長する。
だが、子育ては真似だけでは上手くいかず、試行錯誤の連続になる。
もし子育て経験者なら誰しもロズの苦悩に共感すると共に、「それは当たり前だよね」と子育て先輩の目で見守るでしょう。
キラリは自分の本当の親を死なせてしまったロズを責めず、ロズを親とみなして成長する。
上手くいかない時は他の動物の力を借り、最後は自分の努力で乗り越える。
【変容】
ロズは論理思考なので、理屈が通らないものを始めは理解できない。
だから読み聞かせの空想の物語が理解できず、ハートの大きさという例え話も伝わらない。
でも徐々に生物の感情的で非論理的な知性を理解し、思考が変化していく。
チャッカリも他の生き物も、ロズの利他的な行動に感化され、生存本能以外の感情が生まれ変化する。
【アイデンティティ】
ロズは名前の重要性が理解できない。
だからキラリの名前に番号を付け、「連番じゃないからOKだよね!」としか判断できない。
ロボットは画一的だが、生き物は全員が異なる個性を持ち一緒ではない。
この物語は、”あなたは誰でもなくあなたなのだ” ということを教えようとしている。
【論理と感情】
ロズは頭で機械的に理解しようとするが、最後は心で感じるということに気づく。
それは見せかけの心ではなく、本当の感情的な “何か” から沸き起こる意識です。
恐らく今後もロボットやAIが超えられない部分が最も重要なものなんだと教えてくれる。
【受容】
自然は食物連鎖の縦社会ですが、共通の倫理観や道徳観を持てれば共存できると描いています。
これは人間社会に対する指摘ですが、もしかしたら人間とロボットに対しても言えるかもしれません。
【愛と犠牲】
ロボットはある意味 ”犠牲” の象徴です。
任務を終えたら自ら信号を出し、工場に回収されます。
でもキラリや周囲の動物に対する “愛” が生まれ、寂しさを感じ始めます。
それでも最後は自らが犠牲となり、皆を助けます。
それこそが愛なのでしょう。
犠牲(=工場に戻る)という結末は一緒でも、そこに愛があるか無いかで物語はまったく違ってきます。
【知性】
この物語に人間はほとんど登場せず、ロボットと野生動物のみです。
ロボットは優秀ですが、それは知性なのでしょうか?
野生動物に知性は無く、本能の赴くままに行動する “自然界のロボット” なのでしょうか?
魂とは何でしょうか? 愛とは何でしょうか?
明確に魂があると言い切れないロボットと野生動物でも、相手を思いやる気持ちと愛があれば、心を通わし平和を築くことができる。
つまり、“いわんや人間はどうなのよ?” と、この物語は問いかけています。
2024年のアカデミー賞で「長編アニメ映画賞」確実と思われていましたが、何とラトビアの低予算アニメ『Flow』に敗れてしまいました。
『Flow』は動物のみ、セリフもすべて鳴き声のみという異色アニメですが、なぜ敗れたかは『Flow』を観れば分かります。
どちらも動物メインで似たようなテーマで素晴らしい映画ですが、人は時に饒舌で内容の濃い小説よりも、美しく優れた “詩” に心を打たれるのでしょう。