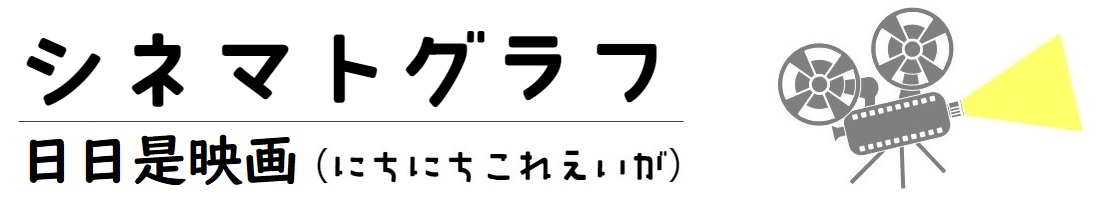| 原題 | Weekend Rebels |
|---|---|
| 製作年 | 2023 |
| 製作国 | ドイツ |
| 監督 | マルク・ローテムント |
| 脚本 | リヒャルト・クロプ |
| 音楽 | ジョニー・クリメック、 ハンス・ハフナー |
| 出演 | フロリアン・ダーヴィト・フィッツ、 セシリオ・アンドレセン、 アイリン・テツェル、 ヨアヒム・クロール、 ペトラ・マリー・カミーン |
アスペルガー症候群の子供を持つとはどういうことでしょうか?
この映画が大袈裟に描いてるとは思えないので、恐らくこの映画と同じように大変なのでしょう。
「もし自分だったら、この両親のように振る舞えるだろうか?」と考えると、恐らくは無理だ。
エレベーターの中の人生
僕たちにできるのは一緒に乗ること
主人公の少年はエレベーターに閉じこもり、ひたすら上下動を繰り返す。
殻から出てこず、歩み寄りが見られない限り、両親にできるのは子供に合わせることだけ。
それは正直きつい…
ただ、サッカーチーム巡りを行うことで、途中から少年にも “少しだけ” 歩み寄りの姿勢が見られる。
その “少し” が、両親にとっては “大きな救い” なのでしょう。
それは成長のせいなのか、サッカー観戦のせいなのかは分からない。
でも、自分が作り出したルールとプランの中だけで生きてきた主人公にとって、目的を果たすためには自分の中のルールやプランを変えざるを得ないと気付けたことが大きかったのかもしれない。
映画の感想はここまでで、脱線ですがアスペルガー症候群に関することを2点。
人類には、なぜ一定数のアスペルガー症候群が存在するのでしょうか。
遺伝学的に見ると、もし生存競争に大きく不利ならその遺伝子は淘汰される可能性が高い。
(遺伝子が原因かまだ不明ですが、遺伝的要因が大きいと考えられている)
それでも太古から一定の割合で発生していたとすると、「実は何か役割があるのでは?」という考えもあるそうです。
種として生き残るために、その特殊な才能を必要としていた可能性があるということ。
僅かな変化に気づいたり、ある領域で高度な知能を有したり、他の個体には無い能力を発揮することで、必ずしも種全体で見た時の生存競争だと不利ではなかったという見方は何となく納得感があります。
もう一つは、精神科や心療内科におけるASDやADHDの診断。
人の性格や思考は数多くの指標が全方位にグラデーションのように広がっていると考えているので、誰しもが何らかの欠陥を持っているはず。
だから、この映画の主人公のように “生活に大きな支障が出る極端な症例でない限り”、診断結果にあまり意味はないと考えています。
私はASDです!ADHDです!と言う方もいますが、そもそもグラデーションなのできっちり線引きできるものではないはず。
そもそもが心理テストだし、ぎりぎりセーフだった人と、ぎりぎりアウトだった人に差なんてない。
それで安心できる、自分を知っておきたいという点は理解しますが、人間は様々な良い点・悪い点が入り混じって出来ているので、周囲も含めて通常の生活が成り立たないほどのレベルでない限り、「発達障害です」というラベルを貼ることには反対です。
(もちろん、特別な対処が必要な人はきちんと認可してケアしてあげることが重要です)